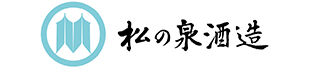9月に入り、人吉・球磨地方の朝晩は、めっきり涼しくなりました。
秋は、もうすぐそこまで来ているようです。
写真中央の「白髪岳(1417m)」に降った雨は、歳月をかけて花崗岩をくぐり抜け、麓の「谷水薬師」に湧出します。
この名水と源を同じくする水が、当社の地下を流れていて、
「松の泉」の焼酎づくりには、この良質な水を使用しています。
- 詳細

球磨郡水上村の霊峰 市房山(1722m)の4合目に鎮座する「市房神社」までの参道には、樹齢千年といわれる20本の大杉が立ち並んでいます。
写真は、市房山で幹周り最大の「平安杉」です。(幹周り約8m、高さ約40m)「市房神社」の建立(807年)が、平安時代であったことから命名されたそうです。
山道をゆっくり歩くと、森の木々の放つ「フィトンチッド」という清々しい香りの成分が、心と身体をリラックスさせてくれます。
※このほど「相良700年が生んだ保守と進化の文化」が「日本遺産」に認定されました。
縁結びの神様として知られる「市房神社」や「球磨焼酎」もその41件の構成文化財に含まれています。
※平安杉 幹が途中で分岐せず美しい樹形が保たれている杉としては、市房山で幹周り最大の杉です。
- 詳細

写真は、球磨郡相良村の役場近くを流れる川辺川です。
太公望が一人アユ釣りを楽しんでいました。
例年、9月には体長30cmを超える「尺アユ」が釣れるそうです。
残暑厳しい折に、アユを肴に球磨焼酎「松の泉」での暑気払い
はいかがでしょう。
※球磨・人吉では、アユの刺身や背ごし(薄くそぎ切りにしたもの)を酢味噌や柚子胡椒で食べます。
- 詳細

- 詳細

写真は「相良三十三観音巡り」の十八番札所「廻り(めぐり)観音」から見た川辺川です。
五木村から下ってきた川辺川は、清流のまま球磨盆地をゆっくりと流れ、相良村柳瀬で球磨川に合流します。
※当社の焼酎蔵から相良村川辺の「廻り観音」までは、車で10数分です。
- 詳細